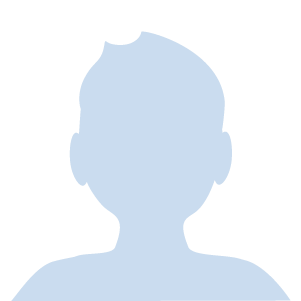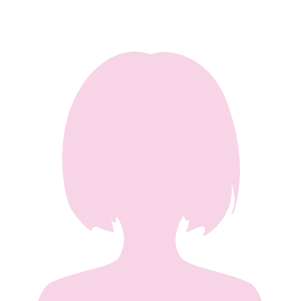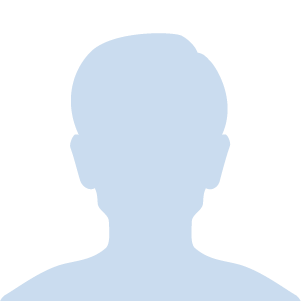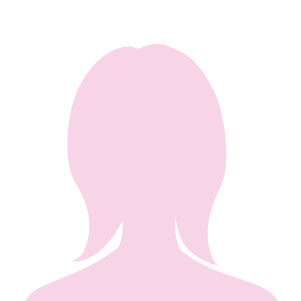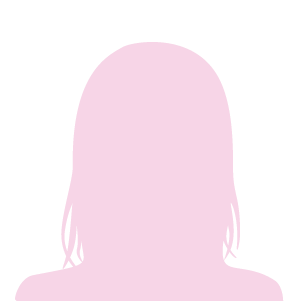「看護動機づけ面接研究会(看護MI研)」について
この研究会では,看護実践を通してともにMIの技術と精神を学び合い,日常の看護ケアの質を高めること,そして動機づけ面接をともに学ぶ仲間づくりを目指しています。
そして,看護師が直面する患者支援の困りごとを動機づけ面接を使って解決するため,動機づけ面接の学習やトレーニングをおこなっていきます。
どんな人が対象?
- 動機づけ面接のことを聞いたり,本で見たことはあるけど,実際に学びたいと思っている看護師
- 患者の行動変容の支援や意思決定の支援をしたい看護師
- 新人スタッフの教育支援や成長支援をしたい看護師(おもに教育担当)
- スタッフの成長を支援したい管理職者(看護師長,看護副部長,看護部長)
活動内容
- 月1回以上のオンライン・ワークショップ
- 対面ワークショップ
- 症例検討会
- 研修企画
- 学会参加(ワークショップ,交流集会,セミナーなどの共同企画・参加)
メンバー紹介(世話人)
講師
藤澤雄太(国立看護大学校 講師・人間科学博士・寛容と連携の日本動機づけ面接学会・常任理事)
田中靖弘(榊原記念病院 師長・心臓リハビリテーション指導士/心不全療養指導士)
オンライン・ワークショップ
興味をもってくださった方に向けて,動機づけ面接入門編と基礎編を作成しました。
「入門編」は、90分の内容となっています(オンライン)。
「基礎編」は全10回,すべてオンラインでおこないます。
動機づけ面接がまだどのようなものなのかわからない方は、ぜひ入門編に一度ご参加いただくのをおすすめしています。
入門編に参加していただき、自分にとって必要なものだと感じて頂いたうえでワークショップに取り組むことで、高い成果をあげることができるでしょう。
\入門編に興味がある方はコチラをクリック/
基礎編については,仕事や家庭で忙しい方も安心して参加できるような工夫をしています。不規則勤務かつ,感染症等で勤務体制の急な変更もあると思います。また,ご家族の予定などもあり,毎週時間を作ったり,週末の午前中にまとまった時間をつくることが難しい場合もあると思います。
そんな方たちが継続学習できるよう,できる限りご支援させていただきたいと思います。ぜひ安心してご参加ください。
そして一緒に学んでいきましょう。
詳細はこちらをご覧ください↓↓↓
\基礎編に興味がある方はコチラをクリック/
動機づけ面接とは
動機づけ面接の定義
動機づけ面接とは,健康な状態に向けて変わっていきたいという患者の言葉を引き出し,その言葉を強めることによって行動変容に向かう支援をするコミュニケーションです。
患者の言葉を引き出していくため,患者とは協働的な関係性を築き,患者が発話しやすい環境を作ることを意識して会話を進めます。
また,とくに患者が発する変わることに向けた言葉(動機づけ面接では,”チェンジ・トーク”と言います)を認識し,その言葉に効果的に反応することによって変わることに向けた意志を強めていくことを目指します。
患者は,自分でチェンジ・トークを発することで,自分が持っている変わりたいという意欲を認識し,行動が起き,継続していきます。
動機づけ面接ではないもの
動機づけ面接の定義をあらためて見てみると、看護師が患者にアドバイスをしたり、関わりによって無理に動機を高めようとしたり、励ましたりすることとは異なることがわかります。
これらの関わり方は、むしろ動機づけ面接の考え方とは反対のアプローチです。
動機づけ面接では、医療の専門家として患者より上の立場からアドバイスをしたり、健康行動を指示したりするのではなく、患者と対等な関係で向き合うことが大切とされているのです。
ときに,患者が言うこと,これまでやってきたことを聞いて,「いや,そうじゃなくて」とか「わかるんですけど,それだと意味がないので,●●してください」と正したくなってしまうことってあると思います。
よかれと思って言う言葉なのですが,この言葉がかえって患者の行動変容に向けた意欲を低下させてしまうのです。
動機づけ面接を学ぶことで,なぜこの言い方がいけなかったのかについて理解することができるでしょう。
看護師の困りごと
私たちが患者さんと関わるなかで,こんなことで悩んだ経験はありませんか?
- 新しい行動を身につけてもらい,退院後も続けて実践してほしい
- 患者さん自身に,主体的に治療法を選んでもらいたい
- 病状は安定しているけれど,もし悪化したときにどうするかを話し合っておきたい
けれども現実には,こうした場面でどう話をすればよいのか戸惑うことも多いものです。
残念ながら,私たち医療者は,これまでの養成課程でコミュニケーションについて学ぶ機会がほとんどありませんでした。
だからこそ,あらためて「患者支援につながるコミュニケーション」を一緒に学んでいけたらと考えています。このサイトを通じて,みなさんとともに学び合い,実践に活かしていきましょう。
患者指導がうまくいかない
患者さんの退院指導を担当したとき,このような困りごとはないでしょうか。
減塩,内服,セルフモニタリング(体重,血圧)など,循環器疾患を患う患者さんには,退院後の生活習慣の改善が必要となります。
入院して治療を行う前の生活を変えて,今度は新たな生活習慣を身につけてもらわないと,患者さんの心機能がさらに悪化してしまったり,あるいは新たな心血管イベントが発生する恐れがあります。
だからこそ,私たち医療者は患者さんに新しい生活習慣を身につけてもらったり,これまでの習慣を変えてもらいたいと思って指導をしています。
でも皆さん,なんかうまくいかないことありませんか?
私たちの指導を聞いてくれる患者さんもいるんですが,こんなことを言われることもあります。
患者さんが「やらない」とは言ってないんですが,どうも手ごたえが感じられなくて,指導がうまくいってないなと感じます…。
あるいは,こんなふうに言われることもあります。
入院中に取り組んだ体重測定や薄味の食事。退院後もやってもらいたいと思うのですが,やってくれるか心配になります。
がんばって指導したけれども,なんだか,自分がやったことが無意味に感じてしまうことも…。
なんでこんなに一生懸命やっているのに,それが伝わらないんだろう。
なんで患者さんは自分の命に関わることをやろうとしないんだろう。
でも,自分の関わり方がいけないのか,患者さんのやる気がないからできないのか。どっちがいけないのかわからない。
動機づけ面接を学ぶことで,これらの疑問を解決することができるでしょう。
どうやって患者さんを変えるのか,を考える前に,私たち医療者の考え方や言動をどのように変えるのかを考えることで,その先に患者さんの行動変容が見えてきます。
患者の思いを引き出せない
治療法の選択や療養の場の決定など,患者さんやご家族にとって大きな分かれ目となる場面において,私たちがいかにして気持ちを引き出していくのかは重要な課題です。
心機能が低下し,体調も悪くなっていくなかで患者さんは難しい選択をしなくてはいけないことがあります。
また,家族も自分の家庭での役割や仕事をしながらどのように患者さんを支援するか悩みます。
どうすれば,患者さんが望む療養生活を支援できるのかを考えると,やはり大事なのか患者さんの思いや価値観です。
患者さんの気持ちを聞かなくちゃいけないとはわかっているんだけれども,うまく踏み込めなかったり,思いを引き出すことができないことがあります。
患者さんやご家族の役に立ててるんだろうかと不安になったり,終末期のケアに関わりたいとは思ってるんだけれどもコミュニケーションが苦手と感じて,ベッドサイドから離れがちになることはないでしょうか。
患者さんにどんな質問をすれば思いを聞くことができるのか。どんな言葉かけをすれば患者さんの気分をポジティブにできるのか。
どこか”自分が何かをやらなければ”と肩に力を入れるのではなく,患者さんは何を大切にし,何を感じ,何を考えているのかに意識を向けて,患者さんの思いを引き出していくことがよいのかもしれません。
動機づけ面接は,患者さんとの関係性をつくり,患者さんが考えていることや大切にしていることを引き出すことができるコミュニケーションスタイルです。
患者の気持ちを引き出すことに難しさや苦手意識がある方のお役に立てると思います。
動機づけ面接を学ぶ
動機づけ面接という言葉を始めて耳にする方も多いと思います。
下のボタンを見て頂き,みなさんの希望に合わせて,興味のあるところからご覧いただきたいと思います。
研修の依頼
動機づけ面接の研修受講希望者募集中
参加希望者,あるいはお問い合わせの方は,下のボタンからご連絡お願いします。